作業療法学科に入学した1年生たち。いよいよ本格的な授業が増えてきました。
4月の中旬に「解剖学」が開講しました。

医学の中でも、もっとも基礎的な学びの一つなのが解剖学。
この解剖学では、まず「骨」(こつと呼びます)を学んでいきます。
人の背中には肩甲骨が存在しています。実はその肩甲骨のにも、部位ごとに名称があります。
授業では肩甲骨をデッサンし、名称を書き入れ、その名称を覚えていく。このように解剖学は進んでいきます。
しかし、名称の丸暗記ではいけません。なぜその名称なのか、その漢字の持つ意味と骨の形を合わせて「理解していく」ことが大切です。

「入学当初から理解する勉強方法を実施していく。」
このことが国家試験合格へ最も近道なのです。

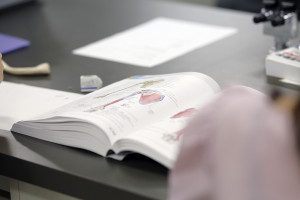
サンビレッジの教員は、詰め込み教育はしません。常に学生が「論理的思考力」を高めながら学んでいけるように、「骨の形はなぜこの形なのか?」を投げかけ、考えさせる機会を与えながら講義を展開していきます。
頭から煙が出るかもしれませんが、クラスメートと支え合いながら、頑張っていってほしいです。
頑張れ作業療法学科1年生!
作業療法学科 教員 廣瀬武
本校3学科の、平成29年度国家試験合格率を報告させていただきます。
介護福祉学科 100%(全国平均70.8%)
作業療法学科 100%(全国平均77.6%)
言語聴覚学科 86%(全国平均79.3%)
お知らせが遅れてしまいましたが、いずれの学科も全国平均を上回ることができました。
地域で活躍できる専門家を育てられるよう、今年度も引き続き努力していきたいと思っています。

この授業では、日本福祉大学健康科学部福祉工学科准教授の渡辺先生を毎年お招きし、コミュニケーションを支援する器機や、それらを操作する装置等を中心に取り上げ、実際の活用事例を概説していただいています。また、操作スイッチの改良等を行うとともに、実際にコミュニケーション器機やタブレット型パソコンを操作しながら、支援技術の視点を理解していきます。

今日は、スイッチの改良です。ハンダゴテとハンダを使い、導線をくっつけていきます。自宅から持参した玩具のスイッチのオン/オフを、簡単なスイッチ操作でできるようにしました。

本当に作業療法士の支援方法は多種多様。様々な方法・技術を学び、患者さんに合った支援ができるように、私たち教員も様々な授業内容を提供していきたいです。
作業療法学科教員 吉田美香
作業療法学科3年生の臨床運動学が開講し、障害を持つ方の歩行分析を行いました。

臨床運動学とは、基本的な人の姿勢、運動、動作及び作業の仕組みを理解し、異常な活動における観察と記録のための技術を身に付ける講義です。
今回は、変形性膝関節症を持つ方の歩行分析を行いました。学生が変形性膝関節症の体験キットを着けて歩行しているのをスロー動画で撮影し、歩行分析を行っていきます。

動画を再生し、問題点となる部分を観察していきます。観察する学生の目は、鋭くて、わずかな変化を捉えようと必死です。

動画が投射されたホワイトボードに問題点を記入し、正常歩行との違いを比較します。
ホワイトボードに記された違いを学生たちは、ディスカッションしながら記録をしていきます。

3年生は来月から2ヶ月間の実習へ行きます。授業で学んだことを臨床の場で発揮出来ることを願っています。
作業療法学科 教員 今井勝紀

本日、平成30年度臨床実習指導者会議が開催されました。作業療法学科新3年生は、学外で臨床実習を2か月間×2回行います。その実習先である病院や施設から実習指導者となる作業療法士の方々をお迎えし、実習の課題などを確認したり、本校の教育方針の確認などを行いました。

会議後には、実際実習に行く学生が指導者に質問をします。
「どんな患者さんや利用者さんがみえるのか」「どんな知識を再確認しておいた方がいいのか。」
様々な質問が飛び交います。学生が情報収集をしっかり行っている姿を見て、私も「段取り八分」の大切さを痛感しました。

会議後の表情もすっきりしています。
いい準備ができていますね。
作業療法学科 教員 廣瀬武